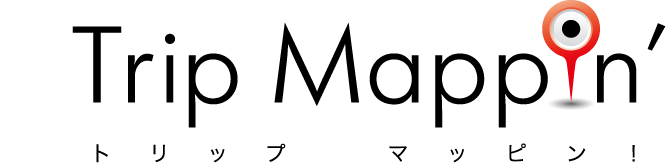備中松山(現在の岡山県高梁市)を舞台に「再建の神様」山田方谷の日本でも類を見ない藩政改革が行われました。このコースは備中松山藩主板倉勝静(かつきよ)の命を受け破産寸前だった藩を救った方谷さんの軌跡を辿るコースです。
明治37年に建てられた、旧高梁尋常高等小学校の本館が郷土資料館になっています。江戸から昭和にかけての生活用具などを展示しており、山田方谷が奨励して盛んに作らせた備中鍬も展示されています。
▼
高梁川に流れ込む紺屋川は、かつて備中松山城の外堀の役割を果たしていました。山田方谷を師と仰いだ、長岡藩士・河井継之助が宿泊した武家宿「花屋」が河畔にありました。 現在、花屋はなく跡地には郵便局が建っています。また、県下最古の教会・高梁キリスト教会堂や藩校有終館跡など情緒豊かな町並みが広がっており、「日本の道100選」にも選ばれています。春には満開の桜を見ることができます。
▼
天保7年(1836) 山田方谷は塾長を務めていた佐藤一斎塾を去る時に、佐藤一斎から「尽己」の書を贈られています。そして、ここ藩校有終館に帰ると学頭(校長)を命じられ、教育と学問に専念しました。山田方谷お手植えの松が5本残っています。
▼
備中松山藩を訪れた河井継之助が方谷弟子入りの許可を得た後、寝泊まりしていた藩の宿です。自炊していたようです。水車も再建されており当時の様子が偲ばれます。
▼
暦応二年(1339)足利尊氏が安国寺として建立した禅寺です。特にその庭園は有名で小堀遠州の築庭と伝えられています。愛宕山を借景とした枯山水蓬莱庭園(鶴亀の庭)で江戸初期の庭園としてはわが国を代表するものの一つです。駐車場の横に「山田方谷先生寓居址」の碑があります。方谷が藩政の激務の傍ら、改革の構想を練り、詩などを作っていた家がありました。
▼
石火矢町は県指定のふるさと村で、武家屋敷の旧折井家と旧埴原家が公開されています。旧埴原家の一角には山田方谷の資料館が設けられています。ここでは方谷の采配や硯(いずれもレプリカ)などを見学することが出来ます。
▼
御根小屋とは藩主の住居と行政用の建物をかねたもので、慶長10年(1605年),備中国奉行・小堀遠州が頼久寺から初めて移り住みました。天和元年(1681年)には水谷勝宗が御根小屋を大改築しました。 現在は当時の建物は残っておらず、跡地には岡山県立高梁高校が建っています。
▼
方谷の私塾「牛麓舎」の跡地です。 現在はなにも残っておらず、跡を記す碑だけとなっています
▼
臥牛山頂上付近に建つ天守は、国の重要文化財で、現存天守を持つ山城としては最も高い所にある天空の山城です。鎌倉時代、有漢郷(現高梁市有漢町)の地頭秋庭重信が大松山に城を築いたのを起源とし、1683(天和3)年に水谷勝宗によって3年がかりで修築されました。当時の姿で現存してる天守、二重櫓、土塀の一部は、中世の貴重な遺構として国の重要文化財に指定されています。白い漆喰塗りの壁と黒い腰板のコントラスト、空の青に映える美しい天守。秋には大手門付近の木々が紅葉し、岩壁が燃えるような朱色に覆われる景色は圧巻です。
▼
天守は国の重要文化財で、現存する12の天守の中では最も高い所にあります。中には囲炉裏が設けられているなど、実戦を想定した作りになっています。
行きたいところを見つける
観光地やお店の見どころやこだわりを知る
自分だけの旅地図を作って予定を立てる
遊びながら旅の予定がまとまっちゃう
 からスタート
からスタート をタッチすると?
をタッチすると?
他のエリアやトップページへ移動します
おまかせ下さい!楽しいモデルコースを提案します
食べる・見る・遊ぶ・買う・泊まる・体験を探す
スポット登録簡単!自分だけの旅地図が作れます
お気に入りのスポットを
マイマップにどんどん登録しよう!
※全ての施設の中が見られるわけではありません